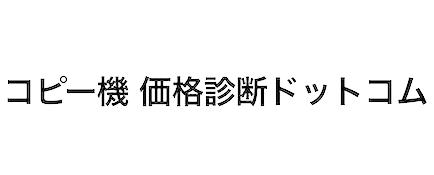【東芝テックの複合機・コピー機】価格相場・保守・機能を解説
Published at2021年11月10日
Updated at
この記事では、東芝テック複合機・コピー機の価格相場や保守、機能について解説します。
▼この記事で分かること
- 東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」の価格相場
- 東芝テック複合機・コピー機の評判・評価
- 東芝テック複合機が向いている企業、向いていない企業
- 東芝テック複合機の導入事例
東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」の導入をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
東芝テック複合機・コピー機の特徴

東芝テックは、日本の三大重電メーカーの一角である東芝の子会社であり、東芝グループとしては唯一、子会社でありながら東証一部に上場しているメーカーです。東芝テックではプリンティングソリューション事業として、コピー機やラベルプリンターなどを製造販売しています。
東芝テック製コピー機のシェア率は、7%程度。2023年5月にはリコーとの協業を発表し、2024年2月にはリコーと新合併会社「ETRIA(エトリア)」に事業を移管すると公表しています。ETRIAの設立は、2024年7月~。
東芝テックのコピー機には「e-STUDIO(イースタジオ)シリーズ」や「Loops(ループス)」と呼ばれる特殊インクを用いたシリーズがあります。主力は、A3カラー複合機の「e-STUDOシリーズ」です。
「e-STUDOシリーズ」は20~75枚機まで揃っており、価格は安価。POP印刷が得意です。ただし、保守体制は充実していません。
▼東芝テック複合機の特徴
- 東芝テック複合機の主力は、A3カラー複合機の「e-STUDIOシリーズ」
- 東芝テック複合機のシェア率は低め
- 東芝テック複合機の価格は安い
- 東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」はPOP印刷が得意
- 東芝テック複合機の保守体制はそれほど充実していない
東芝テック複合機・コピー機の価格相場
ここからは東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」の価格相場を公開します。
「e-STUDIOシリーズ」の価格相場
オフィス用の複合機・コピー機にはメーカーが指定する「標準価格」はありますが、実際の販売価格は標準価格を大幅に下回ります。東芝テック複合機も例外ではなく、それほど安くない販売店でも本体標準価格100万円のコピー機の場合、60~70万円程度まで実際の売値(相場)は下がります。
▼東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」の価格相場
| 印刷速度 | 商品名 | 価格相場 |
| 20枚/分 |
e-STUDIO2020AC | 約53万円 |
| 25枚/分 |
e-STUDIO2525AC | 約79万円 |
| 35枚/分 | e-STUDIO3525AC | 約103万円 |
| 45枚/分 | e-STUDIO4525AC | 約127万円 |
| 55枚/分 | e-STUDIO5525AC | 約153万円 |
| 65枚/分 | e-STUDIO6527AC | 約228万円 |
| 75枚/分 | e-STUDIO7527AC | 約249万円 |
東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」の価格は、同スペック他社複合機と比較して安いのでしょうか?それとも高いのでしょうか?東芝テック複合機「e-STUDIO2525AC」と他社同型機の価格相場を比較します。
▼「MFX-C7250」と他社同型機の価格相場を比較
| メーカー | 商品名 | モデル名 | 価格相場 |
| 富士フイルム(ゼロックス) | Apeos C2570 | Model-P | 約89万円 |
| Model-PFS | 約130万円 | ||
| リコー | RICOH IM C2510 | 約75万円 | |
| RICOH IM C2510F | - | 約99万円 | |
| キヤノン | iR-ADV DX C3926F | - | 約106万円 |
シャープ |
BP-40C26 | - | 約86万円 |
| BP-60C26 | - | 約89万円 | |
| BP-70C26 | - | 約99万円 | |
| コニカミノルタ |
bizhub C251 i | - | 約91万円 |
| 京セラ | TASKalfa 2554ci | - | 約78万円 |
| 東芝テック | e-STUDIO2525AC | - | 約79万円 |
東芝テックの25枚機の価格相場は、約79万円です。東芝テック複合機e-STUDIO2525ACの価格は、他社複合機と比較してもいと言えます。
BTASKalfa2554ciBTASKalfa2554ciP-40TASKalfa2554ciC26P-40C26
東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」のリース料金相場
次に、東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」のリース料金相場について確認しましょう。リース料金相場はリース料率やリース期間に左右されますが、ここでは5年リースで1.9%のリース料率として換算します。
▼東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」のリース料金相場
| 印刷速度 | 商品名 | リース料金相場 |
| 20枚/分 |
e-STUDIO2021AC | 約10,000円 |
| 25枚/分 |
e-STUDIO2525AC | 約15,000円 |
| 35枚/分 | e-STUDIO3525AC | 約19,570円 |
| 45枚/分 | e-STUDIO4525AC | 約24,130円 |
| 55枚/分 | e-STUDIO5525AC | 約29,070円 |
| 65枚/分 | e-STUDIO6527AC | 約42,300円 |
| 75枚/分 | e-STUDIO7527AC | 約47,300円 |
なお、一般的な複合機のリース料金相場は、以下の通りです。
▼コピー機・複合機リース料金相場【印刷速度別】
| 印刷速度 | 最適な月間の印刷枚数 | 月額リース料金の目安 |
|---|---|---|
| 20枚機(20枚/分) | 2,000枚以下 | 11,000円 |
| 25枚機(25枚/分) | 1,000~3,000枚程度 | 16,000円 |
| 30枚機(30枚/分) | 3,000~6,000枚程度 | 18,000円 |
| 40枚機(40枚/分) | 6,000~10,000枚程度 | 22,000円 |
| 50枚機(50枚/分) | 10,000枚以上 | 23,000円 |
>>>詳しくは、「複合機・コピー機のリース料金相場」記事参照
東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」のリース料金相場は、25枚機で15,000円程度です。他社の25枚機複合機のリース料金相場は18,000円程度ですので、リース料金に関しても「安い」と言えます。
東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」のカウンター料金相場
価格相場・リース料金相場ともに「安い」東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」ですが、カウンター料金相場は相場並みで安くはありません。
【東芝テック複合機のカウンター料金相場】
カラー10円/枚・モノクロ1.0円/枚
なお、その他の複合機メーカーのカウンター料金相場は以下の通りです。
▼メーカー別!複合機・コピー機のカウンター料金相場
| カウンター料金 | メーカー名 |
| カラー6円/枚~ モノクロ0.6円/枚~ |
京セラ |
| カラー8円/枚~ モノクロ0.8円/枚~ |
シャープ |
| カラー10円/枚~ モノクロ1.0円/枚~ |
東芝テック ムラテック |
| カラー12円/枚~ モノクロ1.2円/枚~ |
富士フイルム(ゼロックス) キャノン リコー コニカミノルタ |
>>>詳しくは、「複合機・コピー機のカウンター料金相場」記事参照
なお、他社メーカーの場合、相場より安い価格でカウンター料金が提示されることもありますが、東芝テックの場合はカラー10円/枚・モノクロ1.0円/枚が相場であり底値です。事業所の所在地が保守拠点から遠い場合や、月間印刷枚数が極端に少ない場合はカラー10円/枚・モノクロ1.0円/枚より高く設定されることもありますので、ご了承ください。
東芝テックA3カラー複合機「e-STUDIOシリーズ」比較表
東芝テック複合機・コピー機の主力商品であるA3カラー複合機「e-STUDIOシリーズ」の比較表を掲載します。
なお、選び方の基本は自社の「月間印刷枚数」です。今回は、月間印刷枚数ごとにおすすめの機種を比較します。
月間印刷枚数2,000枚前後なら「e-STUDIO2020AC/2525AC」
| 商品名 | 印刷速度 | コピー/プリント/スキャン/自動両面印刷 | FAX | 給紙段数 | 本体重量 | |
| e-STUDIO2021AC | 20枚/分 | 〇 | ▲ | 1段+手差し | 57kg | |
| e-STUDIO2525AC | 25枚/分 | 〇 | ▲ | 2段+手差し | 80kg | |
月間印刷枚数が少なめの事業所には、コンパクトなe-STUDIO2021ACがおすすめです。e-STUDIO2021ACはエントリーモデルながらも、20枚/分の印刷速度で自動両面印刷機能も標準で付帯します。ただし、給紙は1段+手差しのみ。給紙ユニットを増やしたい場合はオプション対応になります。
月間印刷枚数が2,000枚を超えるようなら、もう1ランク上のe-STUDIO2525ACをおすすめします。e-STUDIO2525ACの印刷速度は25枚/分ですので、月間印刷枚数3,000枚程度の事業所でも対応可能。給紙段数も標準で2段+手差しと、約1,300枚搭載できます。
いずれもFAXやフィニッシャーはオプション対応です。
【関連記事】
・【東芝 e-STUDIO2021AC 価格】リース料・カウンター料金
・【東芝e-STUDIO2525AC / 3525ACなどの価格】リース料金・カウンター料
月間印刷枚数5,000~1万枚程度なら「e-STUDIO3525AC/4525AC」
| 商品名 | 印刷速度 | 月間印刷枚数目安 | コピー/プリント/スキャン/自動両面 | FAX | |
| e-STUDIO3525AC | 35枚/分 | 約8,000枚 | 〇 | ▲ | |
| e-STUDIO4525AC | 45枚/分 | 約1万枚 | 〇 | ▲ | |
月間印刷枚数が8,000枚程度までなら35枚機のe-STUDIO3525ACがおすすめです。月間印刷枚数が8,000枚を超えるようでしたら、45枚機のe-STUDIO4525ACを選ぶといいでしょう。
e-STUDIO3525ACとe-STUDIO4525ACとを比較すると、単純に印刷スピードの違いだけでなく、ファーストコピータイムもe-STUDIO4525ACのほうが1秒以上早いため、「体感による印刷速度の速さ」が違います。
ただし、スキャンの読み取り速度はどちらも同じ73ページ/分程度ですので、スキャン作業のほうが多い事業所では価格の安いe-STUDIO3525ACを選んでもいいでしょう。
なお、こちらの機種もFAXやフィニッシャーはオプション対応です。
【関連記事】【東芝e-STUDIO2525AC / 3525ACなどの価格】リース料金・カウンター料
月間印刷枚数が多い事業所には「e-STUDIO5525AC/6516AC/7516AC」
| 商品名 | 印刷速度 | 月間印刷枚数目安 | コピー/プリント/スキャン/自動両面 | FAX | |
| e-STUDIO5525AC | 55枚/分 | 約1.5万枚 | 〇 | ▲ | |
| e-STUDIO6527AC | 65枚/分 | 1.5万枚以上 | 〇 | ▲ | |
| e-STUDIO7527AC | 75枚/分 | 1.5万枚以上 | 〇 | ▲ | |
月間印刷枚数が1.5万枚程度までなら55枚機のe-STUDIO5525ACがおすすめです。ファーストコピータイムはわずか5.6秒(カラーの場合)と、非常にスピーディ。
月間印刷枚数が1.5万枚以上になる事業所には、65枚機のe-STUDIO6516ACか75枚機のe-STUDIO7516ACがいいでしょう。ただ、こちらの2機種の発売年は2018年11月。高速機をお望みなら、富士フイルム(ゼロックス)やキヤノン、リコーといった大手メーカーの最新機種をおすすめします。
【関連記事】【東芝e-STUDIO2525AC / 3525ACなどの価格】リース料金・カウンター料
東芝テック複合機・コピー機の評判・評価
ここからは、東芝テック複合機・コピー機の評判・評価について確認します。
低速機が安いが、高速機は割高
東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」の場合、35枚機までの低~中速機は比較的安価ですが、55枚機以上の高速機になると、他社複合機のほうが安いでしょう。また、機能性の面や保守の面を比較しても、高速機を導入するなら富士フイルム(ゼロックス)やキヤノン、リコーが安心です。
POP印刷や消えるトナーなど独自の技術が光る
他社複合機と差別化を図るべく、東芝テック複合機はPOP印刷など特殊用紙への印刷を得意とします。エコクリスタルやクリアフォルダー、マグネットシートなどにも印刷できるため、ノベルティ作成を内製化できます。
また、「e-STUDIOシリーズ」ではなく「Loops」というシリーズには、一度印刷した文字を消すことができる特殊なトナーを搭載しています。用紙の再利用を促すことにより、環境問題に取り組みます。
保守の評判はイマイチか
当サイトでは東芝テック複合機のメーカー保守の口コミを集めています。ただ、残念ながら東芝テック複合機の口コミ数は少なく、2022年度の1年間でたったの4件しか集まりませんでした。
非常に少ないサンプルにはなりますが、満足度を平均化した結果は5点満点中、4.0点でした。全メーカーのメーカー保守満足度平均値は4.2点です。東芝テック複合機のメーカー保守の満足度は、他社と比較して若干低めと言えます。
ここで4件の口コミの一部を掲載しておきます。
担当者が居なくても、営業時間であれば必ず連絡がつく。故障してから来社までは、1~2時間ほど。
修理完了までの時間はまちまち。長い時は3時間ほどかかっている。部品の交換などであれば、30分ほど。担当者の方は黙々と作業されている。
定期メンテナンスは6ヶ月毎。定期メンテナンスの内容は、正しく動作しているか等。(東芝テックソリューションサービス株式会社関西支社への口コミ)
よくコピー機に問題が起こります。トラブルの修理対応は早く、すぐに来てもらえます。ただ、直している間、コピー機が使えないため、仕事に差し支えます。「壊れないように修理してもらいたい」というのが本音です。(東芝テックソリューションサービス株式会社東部支社への口コミ)
東芝テック複合機のメーカー保守に対する口コミが集まり次第、こちらに掲載いたします。
東芝テック複合機が向いている企業の特徴3選
それでは次に東芝テック複合機が向いている企業の特徴を3つお伝えします。
▼東芝テック複合機が向いている企業の特徴3選
- 月間印刷枚数が少ない
- POP印刷したい
- 消えるトナー搭載のLoopsを導入したい
東芝テック複合機が向いているのは、「低速機の導入を検討している」企業です。東芝テック複合機は特殊用紙への印刷機能に優れているため、POP印刷したい企業にも向いています。また、Loopsは他に類をみない独自性があります。
東芝テック複合機が向いていない企業の特徴2選
次に、東芝テック複合機が向いていない企業の特徴を2つお伝えします。
▼東芝テック複合機が向いていない企業の特徴2選
- 中速機・高速機が必要な会社
- 保守体制に万全を期したい会社
東芝テック複合機の場合、中速機や高速機は若干、割高です。中速機や高速機をお求めなら、富士フイルム(ゼロックス)複合機かキヤノン複合機、リコー複合機をおすすめします。
また、保守体制にも若干不安が残るため、「コピー機がストップしたら困る」場合は保守が充実している大手3社を選びましょう。
東芝テック複合機・コピー機の導入事例
それでは最後に、東芝テック複合機・コピー機の導入事例をご紹介します。今回ご紹介するのはe-STUDIO2021ACの2世代前e-STUDIO2010ACの事例です。
若干、相場よりは高めのリース料金になっています。ただ、カウンター料金は相場並み。東芝テック複合機の場合、他社よりも思い切った値下げ額にならない印象があります。
ただ、東芝テックの保守拠点から近い場合や印刷枚数が多い場合などは、もう少し値下げ幅が大きくなる可能性もありますので、ぜひお問合せください。
東芝テック複合機の価格・特徴まとめ
今回は、東芝テック複合機の価格相場や保守、特徴をお伝えしました。
- 東芝テック複合機の主力は、A3カラー複合機の「e-STUDIOシリーズ」
- 東芝テック複合機にはLoopsもある
- 東芝テック複合機のシェアは低め
- 東芝テック複合機「e-STUDIOシリーズ」には低速~高速まであるが、低速がおすすめ
- 東芝テック複合機の価格相場は、25枚機で約79万円と安い
- 東芝テック複合機のリース料金相場は、25枚機で約1.5万円と他社メーカーより安い
- 東芝テック複合機のカウンター料金相場は、カラー10円/枚、モノクロ1.0円/枚
- 東芝テック複合機は、「低速機を導入したい」「POP印刷をしたい」「消えるトナーに興味がある」企業に向いている
- 東芝テック複合機は、「印刷枚数が多い」「高い保守レベルを求める」企業には向かない
東芝テック複合機を安く導入したいなら、相見積をとるのがおすすめです。相見積をとることで、確実に複合機導入費用は安くなります。ぜひお問合せください。